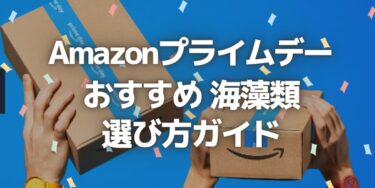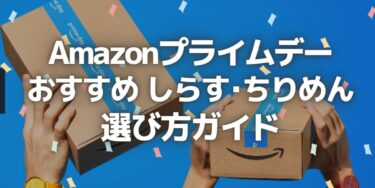うなぎとあなごとはもは全く違う生き物です!
さすがに誰でもご存知とは思いますが、うなぎとはもとあなごはそれぞれ別の生き物です。 それぞれに特徴的な違いがあります。本記事ではうなぎとあなごとはもの違いを解説いたします。
↓の3種類、どれがどれかわかりますか?


生き物としての違い
うなぎってどんな魚?
- 標準和名:ニホンウナギ
- 学名:Anguilla japonica
- ウナギ目ウナギ科
うなぎはウナギ目ウナギ科に分類される魚です。身近なイメージがありますが、実は魚の中でもかなりの高級魚にあたります。流通しているものは99%以上が養殖もの。天然ものは一般にはまず手に入らない超希少品。

天然うなぎの成魚は川に生息しています。川の岩のすき間や石の下などに潜むようにして生きており、カニやエビ、カエルや小魚などなんでも食べる大食漢です。
あなごってどんな魚?
- 標準和名:マアナゴ
- 学名:Conger myriaster
- ウナギ目アナゴ科
あなごはウナギ目アナゴ科に分類されます。江戸前寿司の寿司種には欠かすことのできない魚で、煮つけた身はとろける美味しさですよね。あなごは浅い海に生息しており、日中は砂や泥に潜るようにして生活しています。夜になると砂や泥から出てきて、うなぎ同様カニやエビ、ゴカイや小魚などを捕食します。

はもってどんな魚?
- 標準和名:ハモ
- 学名:Muraenesox cinereus
- ウナギ目ハモ科
はもはウナギ目はも科に分類されます。関西でよく消費されている魚で、京料理には欠かせません。『骨切り』という独特の調理方法で調理される夏が旬の魚です。

どれもウナギ目の魚!かなり広義的には同じ仲間ですが…
とても広い意味で言えば、どれもウナギ目という分類になりますので仲間とも言えなくはありません。ウナギ目に分類される魚たちはどれもうなぎやあなごやはもと同じように細長い体型をしています。ウミヘビ(爬虫類ではなく魚類のほう)やうつぼなどもウナギ目に含まれます。しかし遺伝子分析の結果によると、うなぎはどちらかというとあなごやはもよりも、深海に生息しているフクロウナギやフウセンウナギなどのほうが関係が近いといわれています。

見た目が違う
うなぎとあなごは優しい顔
あなごとうなぎは比較的優しそうな丸みのある顔をしています。一方はもは顔が長く口先が尖り歯も非常に鋭く、触れただけで切れるほどです。
色が違う
はもは緑色っぽい灰色をしています。あなごは茶色っぽい色をしています。うなぎは背中が黒く、お腹が白い色をしています(養殖の場合)。天然のうなぎは全体的に茶色っぽく、お腹は金色をしています。

はもは歯が非常に鋭い
市場でははもを扱う時は軍手をするなど注意を払っています。いけすに入れておく時も、うなぎやあなごは一つのいけすに何十匹も泳がすことができますが、はもは何十匹も入れているとお互いを鋭い歯で傷つけあってしまうため、なるべく少量ずつに分けられていけずに入れられます。
食べ方が違う
あなごはほとんど煮付けにする
あなごは主に寿司種や丼ぶりものに使われる、甘辛い煮付けにされることが多いです。柔らかくフワッとしたあなごの煮付けは好きな方も多いのではないでしょうか。
鱧は骨切りして湯引きにする
はもはほとんど煮付けにすることはありません。夏の旬の食材として用いられるはもは、ほとんどが『骨切り』と呼ばれる小骨を包丁で細かく切る特殊な調理方法を経て湯引きなどにされます。あっさりして上品な甘みのあるはも。東日本ではあまり年中食べられるものではありませんが夏をもたらす魚として知られています。
うなぎはやっぱり蒲焼き
うなぎといえばうなぎの蒲焼です。甘辛いタレにつけて炭火で焼き上げたうなぎは土用の丑の日と呼ばれる夏の時期に大量に消費される、日本の食文化の中でも一大イベントといえるのではないでしょうか。

あなごとはもは天然、うなぎは養殖
はもやあなごは養殖が行われておらず、出回っているものは全て天然ということができます。一方うなぎは出回っているものの99%以上は養殖ものです。天然ものは活きたまま高級うなぎ料理店などに運ばれ、めったにお目にかかることはできません。
なぜはもとあなごを養殖しないのか
はももあなごも天然の資源量が減っています。ではなぜうなぎのように養殖を行わないのかと言うと、うなぎと比べて価格が安いため養殖コストに合わないからです。はももあなごもうなぎと同様に非常に養殖が難しいと言われています。一部では試験的に研究が進んでいるようですが、養殖あなごが一般的に出回るのはまだまだ先の話になりそうです。
うなぎとあなごとはもの共通点
これだけ違いがあるうなぎとあなごとはもですが、もちろん共通点もたくさんあります。特異的なのは『レプトセファルス』と呼ばれる幼生期を経ることです。柳の葉のように薄くペラペラした体型で、海流に乗るのを得意としている体型をレプトセファルスと言います。
うなぎとあなごとはもはどれもレプトセファルスの形態をとることが知られています。あなごのレプトセファルスは「のれそれ」や「どろめ」と呼ばれ、珍味として食べられています。
[amazon-primeday2023-eel]